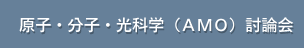
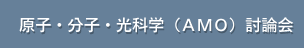 |
|||||
日本初、アジア初の新元素113番が、昨年末に国際機関(JWP:IUPACとIUPAPのジョイントミーティング)で認定され、日本(理研)に命名権が与えられました。同時に115,117,118番元素(米ロ)も認定され、本年は周期表第7周期が完成する記念すべき年になります。元素は科学のもっとも基盤となるものの一つであり、その拡張は、原子・分子を扱う科学全てに大きく影響するものです。本年のAMO討論会でこの超重元素がテーマとして取り上げられること自身意義のあることです。113番元素の製造は、209Bi+70Zn→278113+n反応で作られますが、これまで人類が経験した中で一番反応確率が小さく、8年間で3イベントでした。この極微量の検出を可能にしたのがGARISと呼ばれる反跳核分離装置です。このセッションでは、実際の実験の中核となった若手研究者による生の報告から、非常に長期にわたる研究を支えた精神面から、詳細な研究の中身まで、十分時間を取り議論します。また、同じく重元素科学の分野で最近注目を集めているローレンシウムの初のイオン化ポテンシャル測定についても、実験の中心となった研究者に講演をお願いしました。実験は、超重元素と同じく、加速器で製造したローレンシウムをオンラインでイオン化し質量分析する(ISOL)ことで同定します。その際、表面イオン化法という手法を用いることにより、イオン化効率からイオン化ポテンシャルを求める方法を開発し、初めての実測に成功したものです。現在さらにノーベリウム、メンデレビウムなどにも適応しており、得られたイオン化ポテンシャルはAMO討論会に深く関連する重要なテーマです。ここでは、実測されたローレンシウムのイオン化ポテンシャルに端を発する周期表の再構築の可能性なども含め、科学と化学の基盤となる周期表の拡張について考える機会としたいと思います。
理化学研究所仁科加速器研究センターにおいて合成された113番元素は、IUPAC、IUPAP合同作業部会により2015 年12月、正式に新元素として認定された。今後、日本で最初に命名する元素として元素周期表に記載されることになる。この新元素は、重イオン線形加速器からの70Znビームを209Bi標的に照射し融合反応を起こすことにより、原子番号113質量数278の原子核278113として合成され確認された。2012年までに3例の278113の合成に成功したが、2例は4回の連続したα崩壊ののち自発核分裂を起こし、残りの1例は6回の連続したα崩壊が観測された。それぞれ既知の核に崩壊連鎖がつながっており、その崩壊様式と良く一致している。本講演では、理研における113番元素の合成方法とその結果について紹介し、今後予定されている119番および120番新元素の探索についても紹介したい。
昨年末、113番元素を含む4つの元素の発見が新たに認定され、元素の周期表は第7周期の最後(118番元素:第18族=希ガス)まですべて埋まることとなった。一方で、それらの超重元素がどんな化学的性質を示し、どんな電子配置を示すのか、果たして周期律に従うのか、このような疑問を解き明かす実験も行われつつある。超重元素では、大きな中心電荷に伴う強い相対論効果の影響で、最外殻電子軌道のエネルギーや電子配置が変化し、周期表同族の軽い元素とは異なる化学的性質や電子配置を示すことが期待される。1日に1個、1分間に1個といった生成率で数秒の半減期しか持たない超重元素の物理化学的性質を、如何にして実験的に調べ、どのような情報が得られるか、最近我々が成功した103番元素ローレンシウム(Lr)のイオン化エネルギー測定や、103〜114番元素の化学実験の例などを紹介しつつ概説する。
ゲノムプロジェクトや組織透明化によって生命を構成する分子や細胞の詳細な状態が明らかになるにつれて、生命システムを制御したり、設計したりする試みが始まっています。その一つである合成生物学という生命科学分野は、生命システムを構成する部品(分子や細胞)や環境を操作することで、望みの機能を有する生命システムを再構成・設計することを目指します。本セッションでは、合成生物学に関連する新進気鋭の2人の演者に話題を提供していただき、分子やゲノムをどのようにしてデザインしていくのか、その機会と課題に関して議論します。
タンパク質分子は、生命システムにおける素子として巧みに動作し様々な生命現象を生み出している。望みの機能を持つタンパク質分子をデザインすることが可能になれば、生命を自在に制御・設計することも夢ではない。我々は、タンパク質の立体構造形成や機能発現に関する様々な仮説を立てながら計算機を用いて合理的にタンパク質分子をデザインした後に、それらが実際にどのように動作するのか生化学実験により調べるというアプローチにより、望みの機能を発現するタンパク質分子をデザインする理論と技術を開発している。
近年、様々な機能性タンパク質が合理的にデザインされている。しかし、それらの殆どは、自然界のタンパク質構造を鋳型として、主鎖構造はそのままに側鎖構造のみを作り替えることでデザインが行われてきた。というのも、タンパク質構造を主鎖を含めてデザインするための理論および技術が、まだまだ確立されていなかったからである。我々は、これまでの研究において,タンパク質の立体構造を主鎖を含めて完全にゼロからデザインすることにより、望みの立体構造をデザインするための理論と技術の開発を行ってきた。その結果、タンパク質構造をデザインするためのシンプルなルールを発見し、これらのルールを用いることにより、様々なトポロジーの構造を原子レベルの精密さでゼロからデザインすることに成功した。本討論会では、これらの研究成果と伴に、タンパク質分子デザインから合成生物学への展開について、その将来展望を議論する。
バイオテクノロジーの進展により生命の設計図であるゲノムDNAを操作して天然細胞を改変することが可能となってきた。また、バクテリアからヒトにいたるまで、様々な生物種のゲノム情報が解読され、それらのデータベース化も進んできた。ここ数年の「ゲノム改変」や「ゲノム解読」のための技術革新は目覚しい。さらなる展開の一つとして、蓄積されてきたゲノム情報をもとにデザインされたゲノムを人工合成する技術が考えられる。すでに枯草菌や酵母などの宿主細胞をもちいることで、異種バクテリアのゲノムDNAまるごとを人工的に合成することが可能となってきている。一方で我々は、生物宿主を用いずに、試験管内で簡便にゲノムレベルの長鎖環状DNAを人工合成することができないか検討している。
大腸菌ゲノムは約500万塩対の環状DNAからなり、唯一の複製起点oriCから両方向に複製が進行する。我々は20種以上の蛋白質を用いて、大腸菌ゲノム複製における開始・終結・分離の全サイクルを1つの試験管内に再構成した。この「複製サイクル再構成系」では複製後に絡み合った姉妹環状DNAの分離後、元の環状構造に戻った産物を鋳型として、さらなるラウンドの複製サイクルが繰り返し導かれる。よって、ワンポット等温反応での環状DNA分子の指数増幅が達成される。この反応系はゲノム複製機構をまるごと再現したものであるため、長鎖環状DNAの増幅能にも優れている。本討論会では、「複製サイクル再構成系」を利用した合成生物学的な研究展開について、人工環状ゲノムの試験管内合成の試みも含めて議論させていただきたい。
2016年2月、米国の重力波検出プロジェクトLIGO は、重力波を観測したと発表した。重力波は、アインシュタインが100年前に構築した一般相対性理論の中で予言をした、重力の波動である。しかし、その効果は極めて小さく、それを観測することは不可能と思われていた。約60年前に米国のWeberは重力波を検出するために弾性体の振動を利用した検出器を構築し研究を開始した。1990年代には、巨大なレーザー干渉計を用いた重力波検出器のプロジェクトが世界各地でスタートし、様々な感度向上のための技術開発が進められてきた。そして、ついに検出に成功した。しかも、その結果は、我々の想像をはるかに超えた現象をとらえていた。
日本でも、現在、KAGRAという名前の検出器を岐阜県神岡に建設している。本検討会では、重力波検出の概要を技術的な側面とデータ解析・および理論的アプローチを説明し、重力波天文学の誕生、そして展望に関して議論を進める。
重力波とはアインシュタインが1916年に一般相対性理論に基づいて予言した時空のさざ波である。2015年9月に米国のLIGOが約13億光年離れたブラックホール連星の合体がもたらす重力波の観測に成功し、アインシュタインの予言が正しかったことを証明した。2018年頃までには、欧州のVirgoと日本のKAGRAも観測に加わる予定であり、光やニュートリノでは得られない新しい情報を元にした重力波天文学が始まると期待されている。KAGRAは史上初めて地下に建設された、次世代型の低温重力波望遠鏡であり、最も良い100Hz付近の帯域ではLIGOを凌ぐ感度を有する高いポテンシャルをもった装置である。本講演ではKAGRAの特徴を説明し、その開発の現状を紹介する。
2015年9月14日、advanced LIGOは重力波の直接検出に成功した。GW150914と呼ばれるそのイベントは、太陽質量の36倍および29倍の2つのブラックホールからなる連星系が合体し、3倍の太陽質量に対応するほどの質量エネルギーが重力波として放出されたことによるものと考えられる。おそらくこのような現象は宇宙では稀ではなく、今後重力波によって、ブラックホール時空の性質、中性子星などの超高密度天体の物性、超新星爆発の機構、さらには一般相対性理論の検証など、現在のところ全く未知の物理について研究が進んでいくと考えられる。重力波による天文学が創成される。日本も重力波の国際検出網に加わるべく重力波検出器KAGRAをアップグレード中である。
本講演ではまず、データ解析手法一般について簡単に説明したのち、advanced LIGOが重力波を直接検出した経緯、解析手法、速報システムが果たした役割、電磁波観測網との関係、検出した天体などについて概観する。その後、日本の重力波検出器KAGRAにおけるデータ解析体制を人員、計算機資源、ソフトウェアの面から解説する。重力波は極めて微弱で、その検出は解析においても雑音との戦いである。重力波検出器は20万ほどの補助チャンネル、年間数Petabytesほどのデータをどのように有効活用するか、我々が最近取り組み始めている独立成分分析を用いた多チャンネル解析ついても紹介する。また私自身の専門として、将来の検出を狙っている高速自転中性子星からの連続重力波の検出について、検出手法、検出可能性、および天文学・物理学的な意義を解説する。
軟X線領域の分光法は、物質の電子構造についての情報が得られるため、放射光を光源として物質の化学組成や結合状態を明らかにする目的で広く用いられている。光源である放射光は、パルス幅が数10ピコ(10-12)秒でパルスエネルギーが低いが高輝度のため、現在も広く基礎・応用研究に利用されている。しかし、物質の電子励起後の緩和時間は1ピコ秒未満に及ぶため,励起後のダイナミクスの解明には、パルス幅の短い高強度光源の出現が待ち望まれていた。近年のレーザー技術と電子加速・挿入光源技術の発展に伴い、二つの軟X線領域の高強度光源mすなわちパルス幅が短くパルス当たりのエネルギーが大きい光源が出現した。超短パルスレーザーの高次高調波は、フェムト(10-15)秒より短いアト (10-18) 秒の時間幅を持つ軟X線光パルスが発生可能であり、この光源を用いてアト秒スケールのダイナミクスが報告されている。一方、自由電子レーザーはX線領域において世界最高の集光強度を実現し、X線非線形光学の研究をはじめ、基礎物理学・化学・生命科学分野の研究成果が報告され、また軟X線自由電子レーザーの共用運転が世界で始まっている。二つの高強度光源は、パルス幅と光強度というそれぞれの特長から、現在、新しい研究領域を開きつつある。
本セッションでは、講演1において高次高調波発生した光パルスによるアト秒領域の超高速分光法について、講演2において理化学研究所SACLAにおける軟X線自由電子レーザー光源について、現在最先端の研究をされているお二方にそれぞれご紹介いただき、軟X線領域の高強度パルス光源の持つ可能性とその光源を用いた研究の展開について議論する。
高次高調波は、これまで有効なコヒーレント光源が存在しなかったXUV領域において、実時間分解計測を可能とするフルコヒーレントな光源である。XUV領域の高輝度光源としては、古くは放射光そして最近ではX線自由電子レーザーが知られているが、それぞれ巨大な施設であるという点に加えてパルス幅や波長安定性および繰り返し速度に一長一短があり、実験室規模で高繰り返し可能なフルコヒーレント光源である高次高調波は非常にユニークな存在である。
高次高調波を用いた超高速分光はアト秒領域へと達し、様々な物質の機能や反応に関する我々の理解の地平をひろげつつある。これまで物理化学の分野では、多くの場合、原子核と電子の運動は、その時間スケールの違いからそれぞれ分離されて扱われてきたが,化学反応の素過程を本質的に理解する上では、それらを一貫して取り扱うことが必要で有り、アト秒からフェムト秒領域の高次高調波の出現により、それがようやく可能になりつつある。一方、広いスペクトル帯域を有する高次高調波は、その超高帯域性ゆえに高いエネルギー分解能を得ることは困難であった。そこで超高速性と高いエネルギー分解能を同時に満たす手法として、我々は時間的に分割された2つの高次高調波パルス列を利用したアト秒フーリエ分光法を提案し、これを用いて2原子分子のアト秒量子波束の観測を行った。講演では,アト秒パルス列を用いたポンプ-プローブ法によって得られた最近の知見を中心に、理研におけるアト秒科学の進展を紹介する。
日本のX線自由電子レーザー (XFEL) 施設SACLAは、2012年3月に利用運転を開始し (Ref. 1)、これまで4年以上にわたって堅牢な運転を実現してきた。オングストロームの空間分解能、フェムト秒の時間分解能を兼ね備えた新たなプローブとして、生命科学、超高速化学・材料科学から基礎物理学に至る様々な分野で、最先端の成果を輩出している (http://xfel.riken.jp/research/indexnn.html) 。特に、我が国で開発された高品質のX線集光光学系も援用しながら、X線として世界最高強度の1020 W/cm2が実現された。この超高強度X線を利用して、X線励起による銅Kαレーザーの実現 (Ref. 2) をはじめとする、X線非線形光学・量子光学の研究が大きく進展している。
また、軟X線FELの利用を促進するため、SACLAのプロトタイプ機として建設・運用されたSCSS試験加速器を、SACLAアンジュレータホール内に移設し、SACLAとは独立の電子ビーム源として利用するというプロジェクトを実施している。2015年10月には、波長30 nmの軟X線FELの生成に成功した。今後、加速管の増強による短波長化を図りながら、本格的な利用を進めていく。
1) “A compact X-ray free-electron laser emitting in the sub-angstrom region”, T. Ishikawa et al., Nature Photon. 6 (2012) 540.
2) "Atomic inner-shell laser at 1.5-angstrom wavelength pumped by an X-ray free-electron laser ", H. Yoneda et al., Nature, 524 (2015) 446.
脳の情報処理様式は現行のコンピューターとは質的に異なると考えられ、連想記憶に始まるその研究は我が国でも数十年の歴史が あるが、近年多体系との関係が注目され新しい局面が展開されようとしている。これは同時に、脳よりはどちらかというとノイマン型計算機に近い量子コンピューターのスケーラビリティー(大規模化)に技術的課題が少なくないことが認識されて来た昨今、その状況を打開する新しい方向という意味もある。
今回、ニューラルネットの動作機構に重ね合わせの原理や量子測定に伴う確率過程を導入する「量子論描像ニューラルネット」の研究をされている松井先生、それに「コヒーレント・イジングマシン」による組合せ最適化問題ソルバを研究されている宇都宮先生にご研究を紹介していただく。量子描像ニューラルネットは今のところ現行のコンピューターでシミュレーションを行うもので、その限りにおいては古典コンピューティングに属するが、それでも我々は古典コンピューティングの能力限界を知らないので、現行の能力を凌いで行くためのソフト的方法論として今すぐ使えるという点で、今までになかった突破口になり得る。一方コヒーレント・イジングマシンは物理的実装を試みるものであり、その意味で実装上の課題等がこれから出て来るかもしれないが、量子コンピューターの現状レベルよりはネット化がスケーラブルに思われ、実装できたときに古典コンピューティングそのものを超える可能性もある。お二人のご研究の紹介からこの分野の可能性や展望を議論できれば幸いである。
今年3月中旬に、Google Deep-Mind社の囲碁人工知能”AlphaGo”が4勝1敗でトップ棋士に勝利した驚愕の報道があったのをご存知の方も多いと思う。この人工知能プログラムの勝利はDeep Learning技術がもたらした。これは機械学習の一種であるが、脳の特異な情報処理を実現しようとして古くから研究されているニューラルネットワーク研究から生み出された技術である。機械学習は、ビッグデータ時代・IOT(Internet of Things)時代を迎えた今日、人工知能研究の第3次ブームをもたらしており、その中のニューラルネットワーク研究も装いを新たにして再び脚光を浴びている。Deep Learningの膨大な学習処理、計算コストを克服すべくD-waveの 量子コンピュータを用いた研究も展開されつつある。また、ニューロン(神経細胞)のミクロの構造と量子現象との関連も明らかにされつつある。このような現状を踏まえて、我々が行ってきた量子描像に立脚したニューラルネットワーク研究を紹介したい。このような量子描像ニューラルネットワークはニューラルネットワークの性能向上を希求する試みの一つとして行われてきたが、それがもたらす性能向上は、近年注目されつつある。
カナダのD-wave社は、1998年門脇・西森らが理論的に提案した最適化問題の解法である量子アニーリングを実装した、商用量子コンピュータ(量子アニーリングマシン)を発売している。超伝導量子ビット群にマクロな操作を施すことで、系に実装したイジングモデルの解を自発的に解かせるものである。イジング型の計算機はニューラルネットワークの実装とは相性が良い。1982年にジョン・ホップフィールドが提案した、相互作用がある非同期型のニューラル ネットワークモデル(ホップフィールド・ニューラルネットワーク)は、連想記憶モデルやボルツマンマシンの基本思想となった代表的なものであるが、エネル ギー関数がイジングモデルと等価である。
我々は、イジングモデルを光発振器ネットワークに実装した、組合せ最適化問題ソルバ(コヒーレント・イジングマシン)を提案している[1]。組合せ問題に応じたレーザーネットワークの連結を実装すると、個々のレーザーがイジングモデルの解に対応した発振基底を選んで発振する。レーザー発振することで計算が完了するため、高速に近似解が求まることが期待されている[2]。2012年には、スタンフォード大学を中心に縮退OPOを用いた時分割多重モデルが提案され[3]、最近NTTの稲垣らがファイバー共振器中の4光波混合を用いたN=10,000の1Dリングの実証実験に成功した[4]。実用的な問題を実装するには、スケーラブルなシステム設計が必要となる。現在、大規模化に向けたNTT物性基礎科学研究所と大阪大学との共同研究では、問題数N=2,000を目安にシステムの大規模化に向けた測定フィードバックの実装も進めている。
本講演では、コヒーレント・イジングマシンに関するプロジェクト研究の紹介として、原理説明、数値シミュレーションと実機によるベンチマークによる最新の実験結果を報告する。また開放散逸系であるレーザー・DOPOネットワークを用いてニューラルネットワークで記述される問題も含めてどのような問題を解くべきかなど、今後の展望についても議論を行う。
[1] S. Utsunomiya, et al., Optics Express 19(19) 18091-18108, (2011)
[2] Y. Haribara et al., Entropy 18 (4), 151 (2016)
[3] A. Marandi et al., Nature Photonics 8, 937-942 (2014)
[4] T. Inagaki et al., Nature Photonics, doi:10.1038/nphoton.2016.68 (2016).