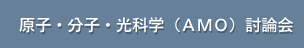
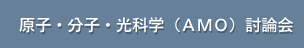 |
|||||
最近専門誌で頻繁に目にしたり、巷で耳にする新しい物理用語の一つにAdS/CFT (anti-de Sitter/conformal field theory) 対応という言葉がある。場の量子論と量子重力理論の間の関係を表すもので、高エネルギー物理学の分野で近年最も多く引用される概念である。とはいわれても、原子分子光科学とはかなりかけ離れた内容であまり関係がない、あるいは無縁であろうから理解する必要はないと個人的にはたかをくくっていた。しかしながら、実はそうでもないらしいことを最近になって認識するようになった。この理論は強結合の場の量子論の研究への強力なツールを提供していて、数学的に扱い易い弱結合の理論に変換することにより、原子核物理学や物性物理学での多くの研究に使われてきている。AdS/CFT対応はBECのような量子多体系物理に展開可能であり、さらにはエンタングルメントエントロピーと呼ばれる量子もつれ合いを測る物理量が、このアイデアを用いると、重力理論におけるある種のエントロピーと同一視できる。このような多くの分野と関係が明らかになってきた状況をふまえて、本セッションでは、二人の最先端の素粒子物理理論研究者の方をお招きして、わかりやすい説明でAdS/CFT対応理論の基礎とその発展をじっくりと伺い、原子分子光科学との関連性の理解を深めたい。
Maldacenaが唱えたAdS/CFT対応予想は、超弦理論から生まれた予想であるが、現在はその応用が、QCDや強相関電子系などにも及んでいる。ここでは、AdS/CFT対応とは何か、をなるべく分かり易く説明し、その応用例や重要性などを説明したい。
AdS/CFT対応とは、ある種の強相関の量子系の極限が、高次元の仮想古典重力理論と等価であるという対応のことである。通常は計算が非常に困難な、量子多体系の計算を、古典重力理論で行うことが出来るため、AdS/CFT対応が使えるような系では計算に大きな威力がある。一方で、AdS/CFT対応は予想であり、数学的な証明が無いため、どのような物理量がどう対応するか、という「辞書」は手探りで研究されて来た。
膨大な研究の結果、クォークを取り扱う量子色力学(QCD)に類似の理論でAdS/CFT対応が非常にうまく機能していることがわかってきた。これには、ハドロンのスペクトルや相互作用、多体系の相図、といった静的な物理量があり、また近年の応用として、強相関量子系にさまざまな時間変化をする外場揺動をかけたときの非線形応答がある。とくに近年の応用のうち、時間変化する電場内の強相関荷電フェルミオンの挙動の解析などを紹介したい。
AdS/CFT対応とは、曲がった空間上の重力理論と強結合な場の理論の間の等価性を指す。この対応はもともと超弦理論の枠内で予想されたものだが、近年はその適用範囲が拡大されている。例えばQCDや物性物理学における強相関系の定性的な性質が、対応すると期待される重力理論を用いて解析されている。一方、エンタングルメントエントロピーは量子多体系の量子的な「もつれ」を測る重要な指標として用いられている。AdS/CFT対応を仮定すると重力理論でもこの指標が計算できるはずだが、実際エンタングルメントエントロピーが時空のある曲面の面積で与えられることが示された。この講演ではエンタングルメントエントロピーが量子多体系でどのように研究されているかを概説し、最近明らかになってきた重力理論との関係性を紹介する。
科学の基礎である計測において、メートル条約加盟国の間では国際度量衡総会で承認された基本単位の定義と実現法に基づく国際単位系(SI)が使用されている。科学の発展には、より空間的・時間的に普遍なものが基本単位の定義として決まっている必要がある。歴史的に長さの単位「メートル」は、原器から、ランプの波長、そして、物理定数の光速度の値による定義へと変わった。しかし、質量の単位「キログラム」の定義は現在でも原器であり、また、温度の単位「ケルビン」は水の3重点という物性値である。これらの単位の定義を、プランク定数やボルツマン定数などの物理定数値に変えようという提案が国際度量衡委員会でなされ、これらの物理定数値の精密測定が精力的に行われた。その先、さらに時間(秒)の定義が18桁の精度の光格子時計の出現により変わろうとしている。本セッションではこのような度量衡の定義の略史と直近に予定されているこれらの再定義について概観し、今後に与える影響や発展性を議論したい。話題提供者としてはプランク定数やボルツマン定数などの物理定数値の測定と再定義に詳しい藤井賢一先生と、秒の定義に詳しい安田正美先生にそれぞれの話題を提供していただく。
多くの単位の定義は科学技術の進歩とともに進化・高精度化してきたが、キログラムだけは1889年に国際キログラム原器(IPK)によって定義されて以来、現在でも人工物に頼る唯一のSI基本単位として残っている。この単位をアボガドロ定数やプランク定数によって再定義するための研究が近年、世界の幾つかの研究機関で進み、X線結晶密度法やワットバランス法によってIPKの長期安定性を上まわる精度で質量を実現することが可能になってきた。産総研におけるアボガドロ定数の測定結果などを交えながら、これらの研究の最新動向について紹介するとともに、ボルツマン定数によるケルビンの再定義、電荷素量によるアンペアの再定義などについても簡潔に紹介する。
1) 藤井賢一、「キログラムの定義改定に向けた質量標準の開発動向」、日本物理学会誌第69巻第9号(2014年9月号)、p.604.
2) 藤井賢一、「SI単位の定義改定をめぐる最近の動き」、精密工学会誌80巻第7号(2014年7月号)、p.625.
時計の進化の歴史を振り返りながら、日本発の最新型原子時計である光格子時計の原理について説明する。光格子時計の世界的な展開と現状に触れた後、2019年頃に予定されている秒の再定義への道筋について説明する。時計進化の背景にある共通の考え方や、進化の原動力となる動機を含めたフィードバックループを示しながら、今後の進化の方向性や応用に向けた道筋についても述べる予定である。
1) "Improved Absolute Frequency Measurement of the 171Yb Optical Lattice Clock
towards a Candidate for the Redefinition of the Second", M. Yasuda et al., Appl. Phys. Express 5 (2012) 102401.
2) "原子時計の発展と秒の定義に係わる国際勧告", 洪鋒雷, 日本物理学会誌 Vol. 69, No. 4, 2014, pp.196.
3) "1秒って誰が決めるの?(ちくまプリマー新書)", 安田正美, 筑摩書房, 2014.
ポイント
分子細胞生物学という研究分野においては、生命を構成する分子同士の相互作用がいかにして生命現象を司るかを解明することを目的に研究を進めてきた。歴史的にその初期には遺伝現象を説明するために「遺伝子」を生命を構成する一つの単位、いわば元素として扱ったが、遺伝子の本体が DNAであることが明らかになり、遺伝子から メッセンジャーRNAを介して様々な機能を持つタンパク質が産み出されることが明らかになるとともに、これらの「物質」の動態の解析によって生命現象を説明することを目指してきた。遺伝子工学という技術的な発展に支えられ、分子生物学は大いに発展した。その一方で、生命現象を「分子」のレベルで理解できているのかというと、実は通常の解析では1011ものタンパク質をまとめて解析しているのが実情である。これを1分子の単位で解析するには顕微鏡技術の発展が不可欠であった。空間分解能や時分解能を高め、さらに真空中ではなく生細胞中で1分子の解析が可能になったのは比較的最近のことである。現在では、細胞内反応に関与する分子数とその分布、反応速度、拡散係数、輸送速度、構造変化などを生細胞で定量的に計測することが可能になっている。本セッションではこの分野の第一人者のお2人に話題を提供していただき、生物学分野における1分子計測に関して議論したい。
細胞の様々な活動は細胞内分子のダイナミクスによって支えられており、各々の分子は複雑な反応ネットワークの中で働いているが、残念なことに個々の分子ダイナミクスの詳細はもとより、それらがどのように組み合わされて細胞活動が発現してくるかは一般に明らかではない。我々は、蛍光顕微鏡を用いた1分子可視化法や相関分光法によって生きた細胞の中で分子の挙動を定量し、計測結果に基づいた数理モデルから細胞内分子ダイナミクスを理解することを目指している。本講演では、1細胞期の線虫胚(受精卵)でみられる細胞極性が、分子ダイナミクスによってどのように維持されているかを解明するための、我々の取り組みとその結果を紹介したい。
単一細胞内の成分分布に有意な偏りが生じて、細胞機能が空間的に分化すること(細胞極性形成)は、単細胞・多細胞を問わず、様々な局面で観察される出来事であり、特に個体発生における形態形成、すなわち1細胞の受精卵が分裂・分化して複雑な個体の形態・機能が生じてくる過程では、その最も基礎的な出来事と言える。多細胞生物の発生の最初期に起こる受精卵の極性形成はPARと呼ばれる一群の蛋白質がつくる反応システムに依存している。我々は、受精卵の後側の細胞表層に集積してくるPAR-2蛋白質の細胞内挙動を1分子計測し数理モデルを作ることによって、PAR-2が、個々の分子は秒単位で動的に振る舞いながら、分子集団としては双安定システムとして数分間以上の細胞極性を維持していることを発見した。
生命現象解明に用いられる1分子計測に関して、化学・物理学分野における計測との大きな違いは、“生きている”生体内における分子の果たしている機能の解明という、“生きている”というキーワードにある。生体分子の果たす機能が多様であるため、そこで用いられる方法も多岐に渡っている。
多くの手法が、まずin vitro研究で用いられ、次に生細胞や生体計測へと展開することが多い。最初に、生体分子研究に用いられる1分子操作計測方法について、概略を紹介する。光ピンセット(レーザートラップ)法、磁気ピンセット法、微小ガラス針法、微小ガラスピペット法、原子間力顕微鏡法(AFM)、高速AFM法、流体力学的方法など、多くの方法が用いられる。生体分子計測に特徴的な点を中心に概観し、応用例として生体高分子のフォールディングに関する計測を簡潔に紹介する。その中で、1分子計測結果に固有な特徴と、そのよってきたる原因について考察する。
これらの方法は、詳細な情報を与えてくれるが、ほとんどがin vitroに用いられている。生体・生細胞内における1分子計測では、1分子イメージングによる定量解析が多用されている。実際の画像を基にその特徴を紹介し、1分子イメージング定量解析から何がわかるかを考察したい。
多様な生体分子機能を、“生きている”状態を反映して解明するためには、他の定量手法との組合せや融合が重要となっている。遺伝子からRNAへと情報を読み出す過程である転写に関し、最近の生細胞内における生体分子反応の蛍光イメージング定量解析の例を紹介する中で、生体内における分子機能の定量に関し議論したい。
After the big bang, temperature of the universe is, on average, decreasing monotonously, although interstellar medium is locally warmed up by stars, and various kinds of explosions. In this session, we review thermal and chemical history of the universe. Then we focus on radio and infrared observations of atomic/molecular gas and dust in the universe. We invite two speakers who are world experts in radio and infrared high-resolution spectroscopy. Their talks not only include scientific results but also include development of innovative instruments.
In our Universe, new stars are forming since at least 13 billion years - and still today - out of dense clouds of interstellar gas and dust. At optical wavelengths, dust absorption prohibits observations of the youngest stars and the process of their formation. In contrast, at 1000-10000 times longer wavelengths, the dust is shining brightly as are molecules from a plethora of different species, some of them quite complex. Since molecules have their rotational spectra at millimeter or shorter wavelengths, the submillimeter wavelength (or terahertz frequency) regime offers optimal opportunities for studies of the cradles of stars and a large variety of other interesting astronomical environments out to the highest redshifts. An inherently interdisciplinary enterprise, frontier submillimeter astronomy crucially depends on laboratory spectroscopy and experimentation, state of the art detector development and modern telescope technology working on the driest sites on Earth, in the stratosphere or in space. An overview of this exciting field will be given, illustrated with newest results. The focus will be on high spectral resolution heterodyne spectroscopy, widely used in the radio and (sub)mm regimes, and its possible extension to shorter (far and mid infrared) wavelengths.
Optical and infrared high-resolution spectroscopy (HRS) is one of the most fundamental tools in astronomy to probe into the physical and chemical structures of all the major astronomical objects from planets, stars, galaxies, to intergalactic medium. In particular, the importance of HRS in the infrared has been widely acknowledged because 1) infrared is rich in atomic/molecular gas lines, 2) infrared light can penetrate through the heavy absorption/scattering by the interstellar dusts, and 3) UV or optical light red-shifts into the infrared for cosmologically-distant objects. In the last decade, there has been significant improvements in sensitivity and efficiency of near- to mid-infrared (1-20 micron) HRS thanks to advances in technologies, such as novel gratings and large-format infrared detectors. I will introduce the recent developments of cutting-edge instruments in this new era of IR HRS, along with the technical basic and the latest scientific results.
スーパーコンピュータ「京」を頂点とする計算資源を用いるHigh Performance Computing (HPC)は、その巨大な計算能力を用いることによって、生命現象の分子基盤である生体高分子の機能発現過程のシミュレーションを可能にする段階に達している。巨大複雑系であるタンパク質は、その中にフェムト秒から秒を越える時間スケールにわたる階層的ダイナミクスを持つため、ただひとつのシミュレーションで全体をカバーすることは現実的でなく、それぞれの時間スケールの現象を接続するマルチスケールの扱いをする必要がある。また方法論の観点からは、化学反応に関わる量子化学(QM)から、運動に関わる古典分子動力学(MM)、さらに長時間、大規模の運動を扱う粗視化モデル動力学(CG)というシミュレーション法をつなぐマルチフィジックスの扱いが必要であるとも言える。
シミュレートすべき生理環境下でのタンパク質は、環境としてブラウン運動をしている水、イオン、脂質二重膜などの中で、階層的ダイナミクスを反映した様々な大きさの振幅を持つ熱揺らぎで特徴付けられる運動をしている。生物機能の発現は、そのような大きな雑音の中の、すぐれて確率的な振る舞いをする多自由度の反応座標上の緩和過程である。そのような問題をどのようにシミュレートし、膨大な自由度の中から、どのようにノイズを切り分けて必要な情報を取り出すのかが課題である。HPCとマルチスケール・マルチフィジックスなシミュレーション手法、そして事前情報としての実験データを用いて、それらの問題をどのように解いて、何を知ることができるのかについて紹介し、今後のHPCの進展に伴って進むべき方向を探っていきたい。
タンパク質分子の機能においては、タンパク質分子の作る触媒場の中で活性化される化学反応、すなわち酵素化学反応が重要な役割を果たす。酵素の触媒活性は一般的に非常に高く、その触媒活性の制御を用いて様々な分子機能が発現する。最近、タンパク質分子に特徴的な遅く大きな構造熱揺らぎが、酵素の高い触媒活に性重要であることが実験的に示唆されているが、直接的な証拠がなく大きな論争となっている。
そのような酵素活性の分子機構を分子シミュレーションにより探るために、近年、広く用いられ成功を収めている手法が、quantum mechanical/molecular mechanical(QM/MM)法である。この方法は、分子軌道法や密度汎関数法などの量子化学的(QM)手法と、生体分子の分子シミュレーションで通常用いられている分子力場に基づく分子力学的(MM)手法をハイブリッドするものであり、化学反応に関わる領域をQM法で取り扱う際に、そのまわりのタンパク質環境の影響をMM法に基づき記述することにより、酵素反応活性に関わる触媒場を非常に効率良く考慮することを可能にする。
しかしながら、QM/MM法の成功の一方で、その限界も明らかになってきた。最も大きな困難は、タンパク質分子に特徴的な遅く大きな構造熱揺らぎを考慮するための十分な統計サンプルが取れないことである。この問題を解決するために、我々は、新規な QM/MM自由エネルギー法(QM/MM RWFE-SCF法)を開発した。本発表では、QM/MM RWFE-SCF法の簡単な解説と共に、Ras-GAP G タンパク質の酵素反応解析への適用を通して見えてきたタンパク質の高い酵素活性における構造熱揺らぎの役割を議論する。これらの酵素では、反応遷移状態生成に伴い、タンパク質の大きな構造変化が観測され、それにより、反応活性化エネルギーが減少し、酵素触媒活性が高まっていることが示された。
また、QM/MM RWFE-SCF法は、新規機能を有する変異体タンパク質の設計に力を発揮する。変異体の設計・解析においては、変異導入によるタンパク質の構造変化を十分考慮する必要があるが、タンパク質の構造熱揺らぎによる緩和を十分考慮することが可能な本手法を用いることにより、より正確な変異体のモデリングが可能となる。本発表では、光操作で用いられる微生物型ロドプシンの色変異体の設計についての研究を紹介する。
生体分子の立体構造は対称性が低く、膨大な数の原子が絡む複雑系である。したがって、その機能発現過程のシミュレーションを行うとすると、必要に応じたスケールで対象をモデル化することが重要となる。電子を扱うときには量子化学計算、原子レベルでは全原子計算、残基レベルでは粗視化計算など、種々のスケールを取り入れたマルチスケール計算により統合的に生体分子の機能に迫るわけである。この講演では、このうち、タンパク質の立体構造変化に焦点を当てた全原子レベルのシミュレーションの例を紹介したい。
分子モーターF1-ATPaseは、ATP加水分解の自由エネルギーを利用して、軸が回転する分子モーターである。ATP加水分解の自由エネルギー利用といっても、タンパク質中のATP加水分解時だけがエネルギーを放出するのではない。ATP加水分解の自由エネルギーは、溶液中において定義されるので、タンパク質へのATP結合、タンパク質中でのATP加水分解、タンパク質からの生成物解離という素過程に分割される。F1-ATPaseは、軸回転に対し、それぞれの素過程が分離されて計測されるという珍しい特性を持つ。このF1-ATPaseの全機能発現過程をシミュレーションしようとすると、ATP結合による構造変化、化学反応過程、化学反応後の構造変化、生成物解離に伴う構造変化のそれぞれを扱う必要がある。これらのうち、様々な立体構造変化に関わる過程を解析するのが全原子分子動力学シミュレーションの役割である。
このような全原子分子動力学シミュレーションをしようとすると、タイムスケールの問題に直面する。共有結合の振動を考慮に入れると、時間刻みはフェムト秒程度にとらねばならず、スーパーコンピュータをもってしても、構造変化の時間スケールであるマイクロ秒からミリ秒の計算を簡単に行うことはできない。そこで、構造変化のパスウェイを探る自由エネルギー計算が重要な役割を果たすことになる。本講演では、F1-ATPaseの素過程における自由エネルギー計算の実例を紹介し、巨大で複雑な生体分子の機能発現過程のシミュレーションの現状と将来展望を議論したい。