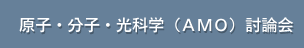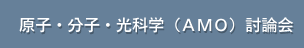セッション3.光による生体操作
(Light-mediated regulation of body functions) |
|
| ディスカッションリーダー:山中 宏二 |
|
| ライフサイエンス分野において、光を用いて生体活動を「計測する」技術や、体内の病変を「可視化する」技術が開発され、基礎研究や臨床研究の発展に寄与している。一方、研究の現場では、計測するだけではなく、より能動的に生体活動を「操作する」ことにより、例えば脳機能など神経活動のダイナミックな理解が可能となってきた。また、光技術によって,能動的に生体内のがん細胞などの生死を「操作する」ことも実験的に可能となった。本セッションでは、光技術を用いた計測技術の進歩を簡単にレビューした後に、脳機能を光技術で操作するオプトジェネティクスを用いた神経科学研究と光線免疫療法と呼ばれる光技術を用いたがんの標的治療研究の第一人者に、それぞれの光技術を用いた研究の最新の知見と今後の展望について解説していただいて、議論を深めたい。 |
|
講演1:光を用いたニューロン活動の時空間操作
(Spatiotemporal manipulation of neuronal activity using light) |
|
| 八尾 寛 |
|
単細胞緑藻類クラミドモナスの光受容タンパク質の一つ、チャネルロドプシン2(ChR2)は、460 nm付近の青色光の吸収にともなう構造変化により、Na+、 K+、 Ca2+、 H+などの陽イオンを透過する機能を有している。この性質に注目し、ChR2などの遺伝子をニューロンに導入・発現することにより、光感受性を新たに獲得させ、光照射のタイミングで活動を操作する新技術(オプトジェネティクス)が生まれた。さまざまな動物のイン・ビボおよびイン・ビトロの系に、この技術を応用することにより、光照射によりニューロン・ネットワークを操作することが試みられている。また、ヒトの網膜色素変性と同様に、遺伝的に網膜光受容体細胞が変性するモデル動物を用いた研究において、ChR2を網膜ニューロンに導入・発現させることにより、視覚が回復することが報告されている。われわれは、ChR2をゲノムに組み込んだトランスジェニックラットを作製した。このラットの後根神経節では、触覚や深部感覚を掌る大型のニューロンでChR2が作られていた。その神経終末は、皮膚に達し、メルケル小体やマイスナー小体などの触覚受容器を構成しているが、ここにもChR2が分布していた。そこで、このラットの足裏に青色LEDの光を照射したところ、光に同期した足の動きが認められた。しかし、赤色の光には反応しなかった。すなわち、このラットの皮膚では、光が触覚受容器の神経終末で受け取られ、活動電位を発生し、脊髄、脳へと伝えられ、触覚としての知覚を引き起こしたことが示唆される。しかし、痛覚、温度感覚をつかさどる小型のニューロンには、ChR2が発現していなかったので、痛覚は引き起こされていないと考えられる。本研究は、世界で初めて、皮膚で光を感知するラットの作製に成功したものである。ものの形、大きさ、動き、手触りなど、触覚から得られる複合的な情報が、脳でどのように認識されているのかは、ほとんど解明されていない。このラットと時空間的にパターン化された光照射を組み合わせることにより、これらの研究が促進されることが期待される。
自然界に存在する光電変換分子と遺伝子組み換え技術により、脳・神経系へ光を媒体とする情報を送り込むことができるようになった。光制御技術、光計測技術、オプトエレクトロニクスを組み合わせることにより、双方向的な脳機能の解読技術の展開が展望される。
ポイント
- チャネルロドプシンは、1個の分子に光受容とイオンチャネル機能を併せ持っている。
- チャネルロドプシンなどの光感受性タンパク質遺伝子を組込むことにより、ニューロンに光感受性を獲得させる技術(オプトジェネティクス)の展開
- 光の時空間パターン照射により、脳・神経系に情報を送達する。
|
|
講演2:光を用いた癌の特異的検出から特異的治療へ
(Seeing and treating cancer in a new light; from molecular specific imaging to molecular specific therapies) |
|
| 小川 美香子 |
|
現在、非侵襲的に癌を検出する手法として、様々な生体イメージング法が用いられている。我々はこれまで、病変に結合する分子と信号(電磁波)を放出する分子とを組み合わせた、分子プローブによる生体イメージング研究を行ってきた。なかでも電磁波として光(蛍光)を利用した分子イメージングは、生体透過性が高くないという欠点はあるものの、生体内で信号のON/OFFが可能な電磁波であることを生かすことで、狙った『癌細胞のみを描出する』極めて特異性に優れた癌の検出が可能であることを示してきた。
最近、この技術を発展させ、分子プローブを用いた光線免疫療法(Photo-immunotherapy; PIT)による特異的な癌の治療法の開発に取り組んでいる。これは、分子プローブが癌細胞に結合し光を当てれば結合した細胞を殺すが、細胞膜に結合しなければ、あるいは、光を当てなければ、いかなる細胞を傷つけることがないという特徴を持ち、正常細胞を傷つけずに『癌細胞のみを殺す』という、副作用の極めて小さい癌治療法である。我々は本法により、マウスに植えた癌をインビボにて迅速に消失させることに成功した。光線免疫療法の抗腫瘍効果の原理については現在検討中であるが、この、狙った細胞のみを生体内から特異的に消滅させる技術は、他の疾患等への応用も期待できると思われる。
本講演では、生体内にていかにして癌を特異的に検出し治療するか、我々のデータを紹介しつつ議論を深めたい。 |
| Top |
|
| 第2日目 2013年6月15日(土) |
|
セッション4.アト秒サイエンスのフロンティア−電子の動きを捉える−
(Attosecond science for capturing motion of electrons) |
|
| ディスカッションリーダー:河野 裕彦 |
|
原子・分子中の電子との非摂動論的相互作用が引き起こす高強度レーザー光は、あらたな原子・分子分光の道具としてのみならず化学反応などにおける電子のアト秒(10-18 s)スケールの実時間運動を追跡する道具として注目を集めている。水素原子の1s軌道にある電子が原子核から受ける引力は、5.1×1011 V/mの電場に対応し、光強度に換算すると3.5×1016 W/cm2である。現在のフェムト秒レーザーはこのような光強度のパルスを発生させることができ、分子内のクーロン力と拮抗する強い力を瞬時に電子に及ぼす精密な道具となっている。強い光電場中では、大きく歪んだクーロンポテンシャルの障壁を電子が透過するトンネルイオン化が起こり,親イオンに再衝突した電子は軟X線の高次高調波を発生する。この広いスペクトル領域のわたる高次高調波を束ねることによってアト秒パルスを発生させることができる。このアト秒パルスは電子の動きの時間スケールに対応しており、そのポンプ−プローブ分光は電子の動きを捉える究極の手段となり得る。また、高次高調波自身の詳細な解析により飛び出してきた電子が関与する分子軌道の時間変化も定量化できるようになってきた。
このような現状をふまえて、本セッションでは、アト秒パルスの発生と応用並びに高次高調波を利用した分子軌道のダイナミクスの追跡に関して第一人者2名を講師として招き、本テーマの現状と可能性について具体例を交えて議論する。 |
|
講演1:レーザー電場のサブサイクル制御による分子内電子の局在化
(Ultrafast laser -induced electron localization in molecules) |
|
| 緑川 克美 |
|
| 物理化学の重要な目標のひとつは、分子間の結合に関わる電子の動きを制御することであり、その結果は、直接的に化学反応や解離生成物の収率となってあらわれる。そのような分子内電子の局在化の制御を光電場で行うには、搬送波位相(carrier-envelope phase: CEP)の制御された数サイクルパルスの超高速レーザーが必要とされてきた。実際に、これまで報告された実験では、ほとんどの場合、パルス幅数フェムト秒でCEPが制御されたレーザーが用いられてきた。しかし、電子の動きと分子を構成する原子核の動きには大きな時間差があり、特に原子核の大きな移動を伴う解離反応では、電子の動きのみならず、核波束の動きに追随して電子の動きを制御する必要がある。今回、我々は、赤外の2波長のレーザーパルスを合成することにより、電子と核波束の動きの双方に追随可能なレーザー電場を生成し、これを用いてH2+分子において90%の電子を一方の核に局在化させることが可能であることを計算により明らかにした。また、20fsというマルチサイクルパルスを用いた方が4fsのパルスよりもより高い電子局在率が得られるという従来の直感に反する結果も核波束の動きを考慮することにより、その理由が明らかになった。さらに、これを3原子分子に発展させた場合の取り扱いとその制御法についても紹介する。 |
|
講演2:再衝突電子を利用した分子内アト秒電子ダイナミックスの測定と制御
(Measurement and control of attosecond electron dynamics in molecules using a re-colliding electron) |
|
| 新倉 弘倫 |
|
化学反応や分子のイオン化過程などに伴い、分子構造の変化(分子を構成する核間距離の変化)だけでなく、分子内の電子状態(電子波動関数・分子軌道)も変化する。1990年代には、フェムト秒レーザーパルスを用いて分子に振動波束を生成し、その時間変化を追跡することが行われた。一方、アト秒科学の時代には、原子や分子の内部を運動する(時間発展する)電子を測定することが目標のひとつとされていた。
アト秒へのアプローチには、主に極端紫外領域の高次高調波をプローブとして用いる方法と、高強度レーザーパルスを原子・分子に照射したときに生じるトンネルイオン化―電子再衝突過程を用いる方法がある[1-3]。トンネルイオン化と電子再衝突過程は、レーザー電場の決まった位相で起こり、電子再衝突によって生じた散乱過程・励起過程[3]・高次高調波発生過程[4]を測定することで、元の原子・分子の電子状態ダイナミックスについての情報を得ることができる。特に、分子から発生した高次高調波スペクトルの強度(・位相)・偏光方向に、分子内を運動する電子波束の情報がアト秒の時間分解能で記載されうる [4]。近年、高次高調波の偏光方向に注目することで、トンネルイオン化過程に伴い炭化水素系分子内に電子波動関数(分子軌道)がアト秒時間スケールで時間発展することを見いだした[5]。講演では、その後の研究の進展も含めて、アト秒分子内電子波束測定と制御について発表する。
[1] Nature millstones,
http://www.nature.com/milestones/milephotons/pdf/milephotons_all.pdf
[2] F. Krausz and M. Ivanov, Rev. Mod. Phys 81, 163 (2009).
[3] Niikura et al., Nature 417, 917 (2002); 421, 826 (2003).
[4] Niikura et al., Phys. Rev. Lett. 94, 083003 (2005) ;105, 053003 (2010);
[5] Niikura et al., Phys. Rev. Lett., 107 093004 (2011). |
|
セッション5.量子凝縮体
(Quantum condensates)
|
|
| ディスカッションリーダー:斎藤 弘樹 |
|
超流動や超伝導はボース粒子が量子凝縮を起こすことに起因している。近年、量子凝縮系として新たに二つの系―――原子気体のボース・アインシュタイン凝縮体・半導体マイクロ共振器中の励起子ポラリトン凝縮体―――が注目されている。
原子気体のボース・アインシュタイン凝縮体は1995年に実現された系であり、ボース統計に従う原子集団を磁場やレーザーで捕獲しマイクロケルビン以下に冷却することで得られる。一方、今世紀に入って実現された励起子ポラリトン凝縮体は、二次元量子井戸を共振器で挟むことで励起子と光子が強結合した系である。ポラリトンの質量は電子の十万分の一と軽く、室温でも量子凝縮を起こすことが可能である。
二つの凝縮体は共にコヒーレントな巨視的物質波であり、超流動性を示す。渦はトポロジカルな位相欠陥として量子化される。従来の超流動液体ヘリウム等と違い、量子渦は光学的に直接観測することができる。また高い実験技術によって多彩な物質波の振る舞いを制御できることもこれらの系の魅力である。他方、二つの凝縮体の間の大きな相違点は、原子気体が熱平衡状態にある閉じた系とみなせるのに対して、ポラリトンは寿命がピコ秒オーダーと短く、非平衡開放系である点である。
本セッションでは、昨今盛んに研究されている二つの量子凝縮体について概観し、それらの共通点、相違点を浮き彫りにすることによって、一方のアイデアを他方に応用したり、相補的な研究を行うことができるかどうかを討論したい。 |
|
講演1:原子気体BECで見る量子流体力学
(Quantum hydrodynamics in atomic Bose-Einstein condensates) |
|
| 坪田 誠(大阪市立大学) |
|
| 原子気体Bose-Einstein凝縮体(BEC)で盛んに研究されているテーマに、量子流体力学がある。Bose-Einstein凝縮を起こした量子流体中では,秩序変数(巨視的波動関数)の出現に起因した量子渦が現れ、その系の流体力学的性質を支配する。このような量子渦が複雑に絡み合って作られる乱流を量子乱流と言う。量子流体力学および量子乱流は、超流動ヘリウムを舞台に約半世紀に渡って研究されてきたが、原子気体BECはその画期的な舞台を提供することとなった。何よりも、最先端の光学技術により、凝縮体を制御し可視化できることがこの系の大きな特徴である。そもそも乱流は,レオナルド・ダ・ヴィンチの時代より、理学・工学を通じて膨大な研究が行われて来たが、十分な解明がなされたとは言いがたく、(古典)物理学の最終問題の一つとも言われている。そのような状況で、原子気体BECの量子流体力学および量子乱流の研究は,自然界の大問題-乱流-の理解にブレイクスルーを起こす可能性があると期待されている。本講演では,(古典)乱流の話から始めて、なぜ乱流が難問なのか,そして原子気体BECはどのような特徴を持ち,その量子流体力学ではどのような研究が行われているかについて、わかりやすく講演する。 |
|
講演2:励起子ポラリトン凝縮とlasing
(Exciton-polariton condensation and lasing)
|
|
| 堀切 智之 |
|
ここ数年我々は励起子ポラリトン凝縮の閾値密度よりかなり上(100倍以上)で観測した場合の実験研究を行っている。その領域までいくと、有効質量が負であるような分散ブランチや高エネルギー側の新しいピークなどの特徴的なPLが観測されてきた。
従来高励起密度でのポラリトンは、密度を上げていく途中で電子-正孔対の結合が破れてプラズマ化し通常の半導体レーザー動作と考えられる実験結果が観測されてきたのだが、我々の結果はそれとは異なる振舞いを示している。
この実験結果を説明する理論はこれまで存在していなかった。近年大阪大の小川哲夫研究室において共振器の寿命を取り入れて、ポンピングと損失を取り入れた非平衡開放系の理論モデルを用いて独自に研究がなされており、PL計算ができるところまで来ている。
本講演では、半導体マイクロ共振器中の量子井戸を用いた励起子ポラリトンの導入から初め、できる限り実験および小川研、分子研鹿野氏らとの共同研究を踏まえた理論の現状も紹介したい。 |
|